
| 教会の紹介 | 集会案内 | 健 康 | 原宿ニュース | お葬式 | 英語学校 | ||
| TIC | 公文教室 | 関連リンク | クリスマス | TOP |
| バックナンバー |

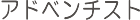
|

|
2005年7月 第223号 
「主イエスを体験する」 安息日学校・第3期聖書研究に寄せて 東京中央教会牧師 長池 明夫 私たちの人生、ぜひとも生き生きとした力で溢れていたいものだと思います。そのためには、その生き生きとした力がどこからくるのかをよく知っておくことが肝要ですし、その力をいつも確保していることはとても大切なことでありましょう。 かつて、あるギリシアの雄弁家はこのように言ったそうです。「活力と正しい判断は心の平安とそれに伴う冷静さからくる」。確かに、私たちは忙しすぎると力を結集することができませんし、感情的になると判断を誤ってしまうことがしばしばです。しかしそのような時、御言葉は私たちに、このように諭してくれるのです。「静まって、わたしこそ神であることを知れ」(詩篇46 : 10)。毎日の生活がバタバタと忙しく、重荷を感じて苛立ち、心配が多くなっていくと、どうしても力が弱くなってしまいます。「しかし、そこに心の静まる領域をつくりなさい。そのことで私たちの心が癒され、また力が それでは、私たちにとって「神を知る」とはどのようなことなのでしょうか? かつて詩篇記者はこのように記しました。「われらの神は高い天にいらせられる」(詩篇5:3)そしてエレミヤは「主は遠くから彼に現れた」(エレミヤ31:3)と言い、さらにヨハネは「言は肉体となり、わたしたちのうちに宿った」(ヨハネ1:14)と記し、そして使徒行伝には「舌のようなものが、炎のように分れて現れ、ひとりびとりの上にとどまったバ使徒行伝2:3)と証ししてあります。 しかしながら、こういった記述は神についてのある種の知識であり、データみたいなものです。ですから、本当に「神を知る」ためには、話を交わし、交わり、共に生活していかなければ分からないのです。聖書では、「知る」ということを、具体的で体験的なものとして扱っています。すなわち「知る」ということは、まず「信頼する」ことであり、「愛する」ことなのです。そして一緒に協力し応答していくことであります。さらに「知る」ということは、主を讃美し祈り、礼拝していくことです。ですから神は、私たちが信頼し、愛し、讃美し、祈り、礼拝していくことで、より豊かに知られ、明らかにされていくお方です。まさに、主イエスを体験していくことで、神の世界を深く知ることができるのです。ですから、私たちの信仰生活には必ず、山を登り谷間を渡っていくような、それぞれ固有なドラマが備えられています。しかしそのような時、私たちは「私たちの只中に住まわれる主がきっと活路を開いて下さる」、このように信頼し、祈り求めていくことができる特権が与えられているのです。そして、そのことは大きな感謝でありますし、その積み重ねが、またさらに主を深く豊かに知るという恵みを与えてくれます。ちなみに、ホワイト夫人が現役を退かれる最後の講演で証しされたことは、私たちにも深い示唆となりました。「私はこの時まで導いて下さった方をよく知っています」。 私たち自身が力を持っているのではありません。主に同化していかなければ「霊的力」をいただくことができません。そして、その同化していく恵みのわざが讃美であり祈りであり礼拝であることを覚えたいと思います。今期の教課の学びを通して、主イエスを体験することが、どれほどの喜びをもたらしてくれるかを分かち合いましょう。 「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しなさい。これが、キリスト・イエスにあって、神があなたがたに求めておられることである」(テサロニケ15:16〜18)。 連載・第7回 歴史のなかの讃美歌(1)  及川 律 聖書の中の讃美歌ということで、3回のシリーズで書かせていただきましたが、今回から「歴史の中の讃美歌」という題で、主に西洋の歴史を追いながら讃美歌の歩みをたどってみたいと思います。 新約聖書が最後に書かれた紀元1世紀後半を過ぎると、徐々にキリスト教は世界宗教として発展していきます。讃美歌はそのなかで、少しずつ新しい地域の信仰と文化を反映しながら育っていきました。残念ながら、西暦300年頃まではメロディーや演奏の方法を記録する手段がありませんでしたが、ギリシヤでは、数学や哲学と共に音楽理論が盛んに研究され、高度な数学のもとにハーモニーの理論やメロディーを書くときの規則などが考え出されました。 4世紀頃のアリストゼヌスという人はピタゴラスの発見した音程の法則を応用発展し、かなり詳しい音楽理論を発表しています。オクターブ、音階、音程、協和音、不協和音、旋法、和声進行などの多岐にわたり、音楽理論を展開しています。このような古代の音楽理論を基礎に、5世紀頃から9世紀頃までに、東方教会と西方教会はそれぞれ独自のチヤント(単旋律の讃美歌)を築いていくことになります。 西方教会では、ローマを中心としたローマ・カトリックの礼拝形式のなかで讃美歌も発展を続けます。ギリシャでは4世紀頃から、聖なるハーモニーや音程という考え方がありましたが、教会のなかではそれをさらに突き詰め、その結果生まれてきたのがグレゴリオ聖歌(西暦800年頃)と呼ばれるものです。教会音楽にふさわしい和音がどういうものかというテーマは、当時から大きな問題で、結局和音なしの単旋律が最も純粋でふさわしいと判断されたようです。このような時期に作られた讃美歌は、のちに和音を加えて現在も親しまれている曲が多くあります(讃美歌−94番、37b番、讃美歌21−229番、339番、72番)。一方、歌詞は文字が作られた頃から記録され、残されていますから、現在でもかなり古いものが残っています(讃美歌−24番、27番、35番、37番、137番、149番、154番)。 次回は、グレゴリオ聖歌をもうすこし詳しく見てみたいと思います。 (つづく) |

